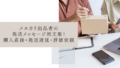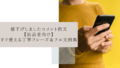小学校の広報誌や学校新聞で欠かせない「編集後記」。
最後の一文で読者の心を温かく締めくくるためには、ちょっとしたコツがあります。
この記事では、編集後記の意味から基本の構成、そして季節や行事ごとに使える例文までを丁寧に紹介します。
文を書くのが得意でなくても大丈夫。
伝えたい気持ちを素直に言葉にすれば、誰でも心に残る編集後記を書くことができます。
読者にやさしく寄り添う文章を、一緒に作っていきましょう。
編集後記とは?小学校での意味と目的
学校新聞やPTA広報誌の最後にある「編集後記」は、読者と編集者をつなぐ大切な文章です。
誌面のまとめとして、読者への感謝や取材で感じたことを伝える役割があります。
ここでは、編集後記の基本的な意味と、小学校でどのように活用されているかを見ていきましょう。
編集後記はなぜ必要なのか?
編集後記は、記事を作った人が「どんな思いでこの紙面を作ったか」を伝える場です。
学校では、子どもたちや先生方、保護者の協力があってこそ紙面が完成します。
編集後記は、その感謝と喜びを読者に届ける“最後の一言”としての役割を持っています。
| 役割 | 内容の例 |
|---|---|
| 感謝を伝える | 協力してくれた人へのお礼を述べる |
| 編集の振り返り | 記事作りで印象に残ったことを共有 |
| 次への意欲 | 次号への期待や抱負を伝える |
学校新聞や広報誌で果たす役割
小学校では、学年通信や広報誌などを通して日々の活動を紹介しています。
その中で編集後記は、文章全体を温かく締めくくり、読者に安心感や親近感を与える部分です。
特に保護者や地域の方が読む場合、子どもたちの様子を編集者の視点で伝えることで、学校全体の雰囲気が伝わりやすくなります。
読者に“温かみ”を伝えるためのトーンとは
小学校の編集後記では、「難しい表現を避け、自然な語り口」で書くのがポイントです。
「〜でしたね」「〜と感じました」などのやわらかい言葉を使うと、親しみが生まれます。
読む人の顔を思い浮かべながら書くと、文のトーンがやさしく整います。
小学校向けの編集後記の書き方【基本の流れ】
いざ編集後記を書こうとしても、どのように構成すればよいか迷うことがあります。
ここでは、小学校の広報誌や学校新聞で使いやすい「3ステップ構成」を中心に、やさしく書くための流れを紹介します。
導入・本文・締めくくりの3ステップ構成
編集後記は、3つの段階で考えるとまとまりやすくなります。
| 段階 | 内容 | 書き方のヒント |
|---|---|---|
| 導入 | あいさつや感謝の言葉 | 「ご覧いただきありがとうございます」など |
| 本文 | 取材や編集で感じたこと | 印象的な場面や気づきを一つ紹介 |
| 締めくくり | 次号への期待や一言 | 「次回もお楽しみに」といった前向きな言葉 |
この3ステップを意識すると、読者に自然で伝わりやすい流れを作ることができます。
「語りかけ文体」で親近感を生むコツ
小学校の広報誌では、堅い文よりも、読者と会話しているような文体が好まれます。
「〜でしたね」「〜と感じました」など、共感を誘う言葉を使うことで、あたたかみが生まれます。
特に、子どもたちや保護者の気持ちを代弁するような表現が効果的です。
季節・行事・テーマを自然に盛り込む方法
季節や学校行事に触れると、文章に臨場感が出ます。
たとえば、春なら「新しい出会い」、秋なら「努力の実り」など、その時期に合ったテーマを取り入れましょう。
| 季節 | 使えるテーマの例 |
|---|---|
| 春 | 入学・新学期・出発 |
| 夏 | チャレンジ・成長・思い出 |
| 秋 | 実り・挑戦・感謝 |
| 冬 | まとめ・振り返り・希望 |
子ども・先生・保護者それぞれへの感謝の伝え方
編集後記で忘れてはいけないのが感謝の言葉です。
小学校では、さまざまな人の協力で紙面が成り立っています。
「一緒に作り上げた」という気持ちを伝えることで、読者との信頼関係が深まります。
- 子どもたちへ:成長や努力をほめる言葉を
- 先生へ:行事や取材への協力にお礼を
- 保護者へ:応援や支援への感謝を伝える
感謝の言葉は短くても、気持ちがこもっていれば十分に伝わります。
小学校で使える編集後記の例文集【行事・季節別】
ここでは、小学校の広報誌や学校新聞で使いやすい編集後記の例文を紹介します。
どの例文も「読者に寄り添うやさしいトーン」と「取材の感想」が自然に伝わる構成になっています。
そのまま使っても、少しアレンジしてもOKです。
入学式号に使える挨拶とメッセージ例
春は新しい始まりの季節です。
入学式号の編集後記では、緊張と期待が入り混じる子どもたちの姿をやさしく描くと良いでしょう。
〈例文〉
新しい学年が始まり、子どもたちの明るい声が校舎に戻ってきました。
入学式では、初めての教室に少し緊張した表情の一年生も、先生や友だちの笑顔に包まれて安心した様子でした。
これからの日々が、笑顔にあふれる素敵な時間になりますように。
保護者の皆さま、地域の皆さまの温かいご協力に心より感謝申し上げます。
運動会・文化祭など行事号の例文
学校行事をテーマにした編集後記では、子どもたちの頑張りや、当日の雰囲気を生き生きと伝えるのがポイントです。
〈例文〉
今年の運動会は、子どもたちが力を合わせて取り組む姿がとても印象的でした。
競技中のまなざしや応援の声には、それぞれの思いがこもっていましたね。
取材を通して、どの学年にも仲間を思いやる温かい心があると感じました。
これからも一人ひとりの成長を応援していきたいと思います。
| 行事 | 文中に取り入れやすい表現 |
|---|---|
| 運動会 | 力いっぱい/応援の声/努力の成果 |
| 文化祭 | 練習の積み重ね/舞台の感動/拍手 |
| 音楽会 | 心を一つに/音のハーモニー/達成感 |
卒業号・学年末号で使える締めの言葉
一年のまとめとなる号では、「振り返り」と「感謝」を中心に構成するとまとまりやすくなります。
〈例文〉
一年間の学校生活を振り返ると、子どもたちの表情や行動の中にたくさんの成長を感じます。
特に、卒業を迎える六年生のみなさんの姿には頼もしさがありました。
この一年を支えてくださった先生方、保護者の皆さま、地域の皆さまに心よりお礼申し上げます。
次のステージでも、自分らしく前に進む姿を応援しています。
地域特集号・特別号に使える一文テンプレート
地域の活動や特別号では、学校と地域のつながりを意識した文章にすると温かい印象になります。
- 「地域の皆さまの協力のもと、子どもたちがさまざまな体験をすることができました。」
- 「これからも地域の一員として、学びとつながりを大切にしていきたいと思います。」
- 「取材を通して、改めて学校が地域に支えられていることを感じました。」
特別号では、普段より少し丁寧な表現にすると印象が引き締まります。
読みやすく伝わる編集後記にする5つのコツ
同じ内容でも、少しの工夫で印象が大きく変わるのが編集後記の魅力です。
ここでは、読者の心に届く編集後記を書くための5つのコツを紹介します。
どれもすぐに実践できるものばかりなので、次に書くときの参考にしてみてください。
文量・語彙・言葉選びの黄金バランス
編集後記の理想の長さは、おおよそ100〜300字程度です。
長すぎると読みにくく、短すぎると伝わりにくくなるため、コンパクトにまとめましょう。
1つのテーマに絞り、短くても伝わる言葉選びを意識することが大切です。
| 項目 | ポイント | NG例 |
|---|---|---|
| 文の長さ | 1文は40〜50文字以内 | 1文が3行以上続く長文 |
| 語彙 | 小学生にも分かる言葉を使用 | 専門用語や比喩の多用 |
| 構成 | 3文構成(導入・感想・まとめ) | 起承転結を無理に意識 |
エピソードを一つ入れるだけで印象が変わる
短い編集後記でも、具体的な出来事を一つ入れるだけでリアリティが増します。
たとえば、「練習の合間に見せた笑顔が印象的でした」など、実際の場面を描写すると、読者の共感を呼びます。
“見たこと・感じたこと・伝えたいこと”を一文ずつ入れるのがコツです。
誤字脱字チェックよりも「読み返し感情チェック」
文章を見直すとき、誤字脱字だけでなく「気持ちが伝わるか」を確認しましょう。
声に出して読んでみると、自然な流れや語尾のリズムが分かります。
文法よりも“伝わる温度”を優先して整えると、印象がより温かくなります。
文章に“リズム”を生む改行と句読点の工夫
読みやすさを決めるのは、内容よりも「見た目のリズム」です。
1文ごとに改行を入れることで、スマートフォンでもストレスなく読めます。
句読点を適度に入れて、呼吸を整えるような文の流れを作りましょう。
- 改行は「1文ごと」が基本
- 句読点は多すぎず、自然な間で使用
- 段落ごとにテーマを区切る
「伝えたい思い」を一文に凝縮するテクニック
編集後記の締めの一文は、読者に最も残る部分です。
言いたいことを長く並べるよりも、印象に残る言葉を一つ選びましょう。
最後の一文は、「ありがとう」や「これからもよろしくお願いします」など、気持ちのこもった言葉で終えるのが理想です。
よくある質問Q&A|編集後記で迷いやすいポイント
編集後記は短い文章ですが、書く人によって悩みが異なります。
ここでは、実際によくある質問をQ&A形式でまとめました。
自分の悩みに近いものを参考にして、スムーズに書き進めてみてください。
Q1:「長すぎる」ときはどう短くすればいい?
文章が長くなってしまうときは、「言いたいことを一つに絞る」のがコツです。
複数の話題を盛り込みすぎると、読み手の印象がぼやけます。
「最も伝えたいことは何か」を決め、それ以外の文を思い切って減らしましょう。
1つの号で1テーマに絞ると、自然に読みやすくなります。
| NG例 | 改善例 |
|---|---|
| 運動会も文化祭も修学旅行も印象的でした。 | 運動会の笑顔が特に印象的でした。 |
Q2:「感想が浮かばない」ときの対処法
文章が思いつかないときは、まず「どんな場面を覚えているか」を考えてみましょう。
印象的だったシーンや子どもたちの表情を思い出すと、自然と書く内容が見えてきます。
難しく考えず、「あのとき感じたこと」をそのまま言葉にすれば十分です。
“上手に書く”より“気持ちを伝える”を意識するのがポイントです。
Q3:「書き手が複数人いる場合」はどうまとめる?
複数の担当者が交代で編集後記を書く場合、全体のトーンをそろえることが大切です。
事前に「文字数」「文体(です・ます)」「結びの言葉」を共有しておくと統一感が出ます。
| 項目 | 共有ポイント |
|---|---|
| 文体 | 全員「です・ます」調で統一 |
| 文量 | 100〜300字を目安 |
| 締め方 | 「ありがとうございました」など感謝で終える |
複数人で担当する場合でも、同じリズムや語調を意識するだけで、誌面全体の印象がぐっと整います。
Q4:「毎号同じような内容」になってしまうときは?
似た話題が続くときは、切り口を少し変えてみましょう。
たとえば、「取材して感じたこと」だけでなく、「読者への呼びかけ」や「次への期待」を加えると新鮮になります。
- 「今回は〇〇に注目して取材をしました。」
- 「取材を通して感じた“子どもたちの変化”をお伝えします。」
- 「次号では、さらに成長した姿をお届けしたいと思います。」
ほんの少し視点を変えるだけで、文章に新しい風が吹きます。
まとめ|編集後記は“読む人へのお礼状”
ここまで、小学校の広報誌や学校新聞で使える編集後記の書き方と例文を紹介してきました。
最後にもう一度、編集後記を書くときに意識したい大切なポイントを振り返っておきましょう。
| ポイント | 意識すべきこと |
|---|---|
| 目的 | 読者に感謝と想いを伝える |
| 構成 | 導入・本文・締めくくりの3段階 |
| 文体 | やさしく語りかける「です・ます」調 |
| 内容 | 具体的な出来事や気づきを1つ入れる |
| 締めの言葉 | 感謝や次への期待を添える |
文章の完成度よりも心のこもった言葉を大切に
編集後記は、上手に書くことが目的ではありません。
「この紙面を読んでくれた人にありがとうを伝える」、それが一番の意味です。
多少言葉が不揃いでも、気持ちがこもっていれば、それが何よりの魅力になります。
“心を込めた一言”こそが、読者の記憶に残る編集後記になります。
次に書くときに意識したい3つのこと
次号や次年度に編集後記を書くときには、次の3点を意識してみてください。
- 文章に“変化”をつけて、毎号違う視点を意識する
- 感謝の対象を少しずつ変えてみる(先生・子ども・保護者など)
- 行事や季節を通じて感じた“温度”を言葉にする
この3つを続けることで、編集後記が「書く人の成長記録」としても残っていきます。
そして何より、読む人に「また次も読みたい」と思ってもらえるような紙面作りにつながります。
編集後記は、読む人への“お礼状”のような存在です。
形式よりも、心をこめて書くことを大切にしながら、次の広報活動に活かしていきましょう。